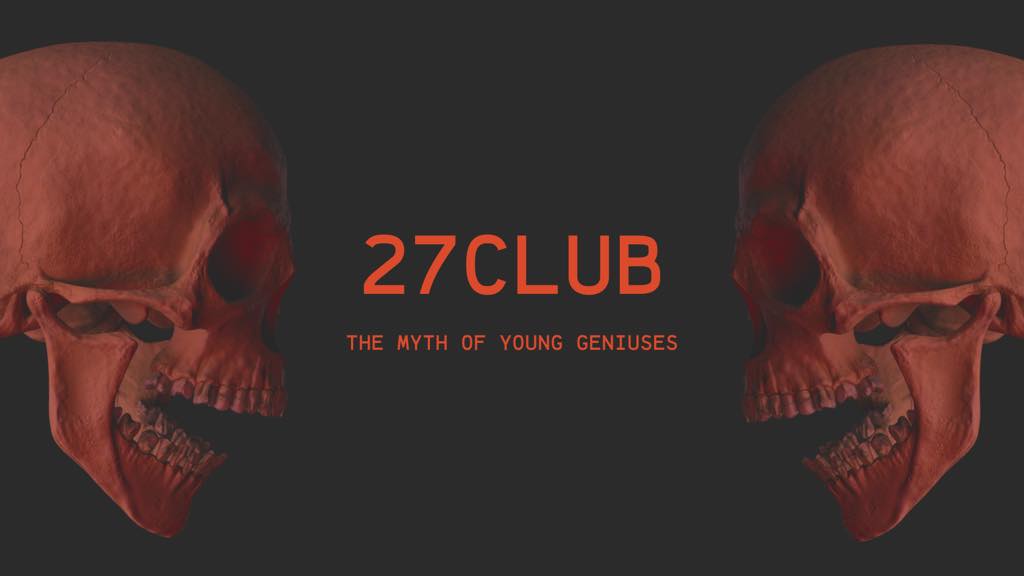
1994年4月、アメリカ・シアトル。ある一報が世界を駆け巡った。ニルヴァーナのフロントマン、カート・コバーンが自宅で自死したのである。享年27歳。彼の死は、1960~70年代に形成された「27クラブ」という神話を再び蘇らせるきっかけとなった。ブライアン・ジョーンズ、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、ジム・モリソンらが築いた伝説に、カート・コバーンという新たな象徴が加わった瞬間であった。
90年代という時代の地層
1990年代初頭、アメリカの若者文化は大きな転換点を迎えていた。レーガン政権期の保守的な価値観や80年代のバブル的な享楽主義に対し、シアトルを中心とするグランジ・ムーブメントは「倦怠」「無気力」「閉塞感」を前面に押し出した。大量生産されたポップ・アイドルやヘアメタルにうんざりした世代にとって、ネルシャツを羽織り、くたびれたスニーカーでステージに立つニルヴァーナの姿は新鮮であり、また自らの姿を投影できる存在であった。
──1991年にリリースされたこの曲は、まさに「ジェネレーションX」のアンセムであり、無気力でありながら怒りを内包する時代精神を爆発的に表現していた。
カート・コバーンの内面
だがカート・コバーン自身は、成功を手にした瞬間からその名声に苛まれることとなる。もともと繊細で傷つきやすい性格であった彼にとって、ニルヴァーナの世界的ブレイクはむしろ重荷であった。アンダーグラウンドで支持されていたバンドが一夜にして「世界最大のロックバンド」となったことは、彼の自己像を大きく揺さぶった。
インタビューでは「自分はただのパンク・キッドに過ぎない」と語り、巨大化する名声に強い違和感を抱いていた。うつ病や慢性的な胃痛、そしてヘロイン依存も彼を追い詰めた。愛妻コートニー・ラヴとの関係も複雑に報じられ、メディアは彼の私生活を執拗に追いかけた。
「27歳の呪い」が再び呼び覚まされた瞬間
1994年4月5日、カート・コバーンはショットガンを手に自らの命を絶った。27歳であった。彼の死が伝えられるや否や、世界中のメディアは「27クラブ」という言葉を再び持ち出した。
ヘンドリックス、ジョプリン、モリソンの系譜に、カート・コバーンが連なるという物語が構築されたのである。死によって彼は「最後のロックスター」「グランジの殉教者」として神話化されていった。
──MTV Unpluggedでのこの演奏は、まるで遺書のように聴こえると多くの人々が語った。死後、そのパフォーマンスは新たな神聖性を帯びることとなった。
名声と死の二律背反
ここで重要なのは、カート・コバーンの死が「名声と死」というロックの二律背反を鮮烈に示したことである。名声を手にすることは同時に孤独と重圧を背負うことを意味し、それが27歳という年齢で爆発するかのように見える。
心理学的に見れば、20代後半は「アイデンティティの再構築」の時期であり、社会的な役割と自己像の調和が求められる。しかし、カートのように20代前半で世界的名声を得てしまうと、この調和は極端に困難になる。自分が誰であるのか、自分の音楽はどこに属するのか──その問いに答えられぬまま、名声だけが先行してしまったのである。
「ジェネレーションX」と死の共鳴
カート・コバーンの死は、当時の若者世代に深く突き刺さった。冷戦の終結後、未来に対する明確な希望を持てなかったジェネレーションXにとって、彼の死は「代弁者の喪失」であると同時に、「自らの倦怠感の極北」を突きつけられる出来事であった。
「Smells Like Teen Spirit」で表現された無気力な叫びは、死によって永遠のものとなり、若者たちの虚無感を正当化するかのように機能した。
メディアと神話化のスピード
1960~70年代におけるヘンドリックスやジョプリンの死も衝撃的であったが、1990年代はメディア環境が大きく異なっていた。24時間ニュース、MTV、雑誌文化の隆盛は、カートの死を瞬時に世界規模で神話化させた。彼の写真、未発表音源、日記、そしてコートニー・ラヴの存在までもが「27クラブ」の物語を補強する素材として消費された。
このメディアによる神話化のスピードと強度は、のちに2011年のエイミー・ワインハウスの死においてさらに加速することになる。
27クラブにおける新たな位相
カート・コバーンの死によって、「27クラブ」は単なる偶然の集合体ではなく、「若き天才の殉教」という様式美として確立した。彼の死を境に、「アーティストは27歳まで生きられないのではないか」という言説が、ロックファンの間で再び語られるようになったのである。
このことは同時に、アーティストの生と死を消費する文化がいかに根深いかを示している。27クラブは、単なる数字遊びではなく、「死と名声の接点」を象徴する文化的装置となったのだ。
まとめ
第2回では、カート・コバーンの死がいかにして「27クラブ」を再定義したかを見てきた。彼の死は90年代の時代精神と強く共鳴し、名声と死の結びつきを鮮烈に印象づけた。次回は2011年、エイミー・ワインハウスによって再び現代的な意味を持った「27クラブ」の物語について掘り下げていきたい。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。








