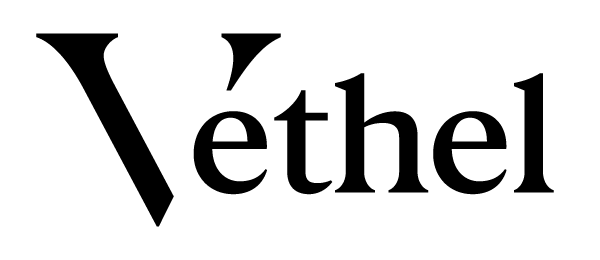ジャズは20世紀初頭のアメリカで誕生し、その後100年以上にわたり進化を続けてきた音楽である。ニューオーリンズの街角で生まれた即興演奏は、やがてスウィング時代のダンスミュージックへと発展し、ビバップによって知的な芸術へと昇華された。さらに、モード・ジャズやフリー・ジャズが新たな表現を切り拓き、フュージョンやスムース・ジャズが多様なリスナーへと広がっていった。
そして2000年代以降、ジャズはヒップホップやエレクトロニカ、ワールドミュージックと融合しながら、新たな時代を迎えている。ロバート・グラスパーやカマシ・ワシントンが現代ジャズを牽引し、UKジャズシーンではシャバカ・ハッチングスやアルファ・ミストが独自の進化を遂げている。
今もなお変化し続けるジャズ。その歴史を紐解きながら、音楽の魅力と未来を探っていこう。
2000年代以降、ジャズは再び大きなうねりの中に身を置いている。伝統への回帰と前衛的な実験精神、そして他ジャンルとの境界を意図的に曖昧にする動きが同時に進行し、ジャズはもはや「ジャンル」という固定された枠組みを軽やかに飛び越える存在となった。鍵となるのは、「融合」である。ヒップホップ、R&B、エレクトロニカ、アフロビート、さらにはグライムまでを取り込みながら、現代ジャズは新たな「語り方」を模索してきた。
こうした現代のジャズ・シーンにおいて、ロバート・グラスパー、カマシ・ワシントン、スナーキー・パピー、そしてシャバカ・ハッチングスらの名は決して外せない。彼らはそれぞれ異なる文脈を生き、異なる文法で音楽を紡ぐが、そのすべてが「現代ジャズの多様性と可能性」を体現している。
ロバート・グラスパー ── ヒップホップとの対話から生まれる新たな即興
現代ジャズの顔ともいえる存在が、ピアニストでありプロデューサーでもあるロバート・グラスパーである。彼が提示したのは、ジャズの即興性とヒップホップのビート、そしてR&Bやネオ・ソウルのグルーヴを融合させた、いわば「21世紀型の黒人音楽」とも言えるスタイルであった。
代表作『Black Radio』シリーズでは、エリカ・バドゥ、コモン、モス・デフ(現ヤシーン・ベイ)、レイトン・グリーン、そしてケンドリック・ラマーといった錚々たるアーティストたちとのコラボレーションを展開。ジャズ・クラブのステージから飛び出し、ストリートの空気と共振するようなサウンドは、従来のジャズファンのみならず、ヒップホップ世代にも深く刺さった。
グラスパーの音楽には、複雑なコード進行や変拍子といった伝統的ジャズの素養が確かに存在する一方で、メロディの明快さと感情の流れに重きを置いたアプローチが貫かれている。そこには、「ジャズは誰のための音楽か?」という問いへの、彼なりの解答がある。
カマシ・ワシントン ── スピリチュアル・ジャズの再興者
一方で、カマシ・ワシントンは、よりスケールの大きなヴィジョンでジャズを語るサックス奏者である。ジョン・コルトレーンやファラオ・サンダースを彷彿とさせるその音楽は、単なるノスタルジーではなく、スピリチュアル・ジャズを現代に甦らせた力強い声明であった。
2015年に発表された3枚組の大作『The Epic』は、そのタイトル通り壮大なスケールを誇る作品である。大人数のバンド編成、オーケストラとコーラスの導入、そして黒人の歴史や哲学を織り込んだテーマ性は、まさに現代の叙事詩であった。
ワシントンの音楽は、即興演奏のスリルを内包しつつも、どこか映画音楽的な構築美を持ち、聴き手を精神的な旅へと誘う。彼もまた、フライング・ロータスやサンダーキャット、ケンドリック・ラマーといったアーティストたちと連帯しながら、ジャズの外へと歩み出している。
スナーキー・パピー ── ジャンル横断型フュージョンの現在地
グラスパーやワシントンが都市の空気と精神性に根ざしているのに対し、スナーキー・パピーはより多国籍で実験的なアンサンブルである。ベーシストのマイケル・リーグを中心に2004年に結成されたこのバンドは、ジャズ・フュージョンを核としつつ、ファンク、ロック、ラテン、アフロ・キューバン、インド音楽といった多様な要素を取り込みながら、アンサンブルの可能性を追求している。
代表作『We Like It Here』では、ライブ・セッションの臨場感そのままに、驚異的な即興演奏と緻密なアレンジが繰り広げられる。とりわけ「Lingus」で聴かれるキーボーディスト、コーリー・ヘンリーのソロは、現代ジャズ史に残る名演として語り継がれている。
彼らの音楽は、ジャズの文法を守るというよりも、そこから自由になることで新たな地平を切り開いている。その意味で、スナーキー・パピーは「脱ジャンル」時代の象徴ともいえる存在である。
UKジャズ ── ロンドン発、グローバル視点のジャズ・リヴァイバル
この20年で最も注目すべき潮流の一つが、イギリス ── とりわけロンドンを中心に勃興したUKジャズ・ムーブメントである。ジャズとアフロビート、グライム、カリブ音楽、ヒップホップといった多様な文化が混ざり合うロンドンの地で、まさに「越境するジャズ」が生まれている。
サックス奏者シャバカ・ハッチングス率いる「サンズ・オブ・ケメット」は、その代表的存在である。アフロ・カリビアンのリズムとポリリズム、政治的メッセージを織り込んだ演奏は、まさにジャズの社会的可能性を今に引き継ぐものである。
さらに、ピアニストのアルファ・ミストは、より内省的かつメロディアスなアプローチで、UKジャズの別の顔を提示している。彼の『Antiphon』や『Structuralism』は、ジャズとビート・ミュージックの美しい融合として高く評価された。
ドラマーのモーゼス・ボイドは、ジャズ・ドラムのフリーな語法に、エレクトロやダブの質感を加えることで、UKジャズにクラブ・カルチャーとの接続点を与えている。彼らの活動は、ジャズが「都市の音楽」として進化し続けることを明確に示している。
終章 ── ジャンルの未来を拓く音楽
こうして見てくると、現代ジャズはひとつの明確な方向性を持っているわけではない。むしろ、それぞれのアーティストが独自の問いと向き合い、自らのルーツや社会背景、音楽的影響を音に変えている。ロバート・グラスパーは都市のリアルと対話し、カマシ・ワシントンは精神世界を紡ぎ、スナーキー・パピーは世界中のリズムを再構築し、UKジャズの担い手たちは都市の多文化性を音に刻む。
ジャズは今、かつてないほどに多様で、そして自由である。音楽は時代を映す鏡であると同時に、その未来を指し示す羅針盤でもある。2000年代以降のジャズは、その両義性を見事に体現しながら、変わり続ける世界の中で、新たな美を探求している。
この先も、ジャズは「変わり続けること」によってこそ、生き延びるだろう。そしてそれは、次なる革命をすでに準備している証でもある。

Jiro Soundwave:ジャンルレス化が進む現代音楽シーンにあえて一石を投じる、異端の音楽ライター。ジャンルという「物差し」を手に、音の輪郭を描き直すことを信条とする。90年代レイヴと民族音楽に深い愛着を持ち、月に一度の中古レコード店巡礼を欠かさない。励ましのお便りは、どうぞ郵便で編集部まで──音と言葉をめぐる往復書簡を、今日も心待ちにしている。