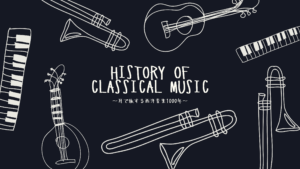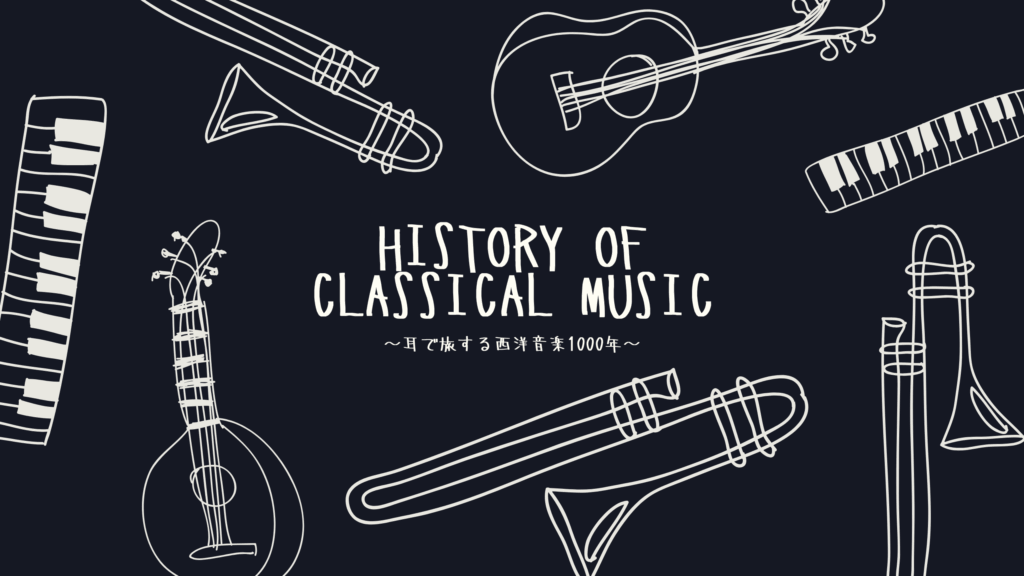
音楽は、どこから来て、どこへ向かうのか。
「クラシック音楽」と聞くと、あなたはどんなイメージを抱くだろうか。
堅苦しい、難しそう、あるいは昔の音楽 ── 。けれど、それはほんの一部に過ぎない。
クラシック音楽とは、9世紀の祈りの声から始まり、劇場、宮廷、戦場、そして映画館やスマートフォンの中へと受け継がれてきた、“人間の感情と思想のアーカイブ”である。そこには、ただ美しいだけではない、問いや葛藤、時代のうねりと個人の叫びが、確かに息づいている。
この全8回の連載では、中世から21世紀まで、クラシック音楽の歴史を大きく8つのフェーズに分けてたどる。バッハも、ベートーヴェンも、ジョン・ケージも、決して遠い存在ではない。彼らの音楽は、時代を超えて今も私たちの耳に届いている。
音楽は、いつも変わり続ける。
だからこそ、過去を知ることは、未来の音をもっと自由に聴くためのヒントになるはずだ。
クラシック音楽の1000年を、あなたの耳で旅してみよう。
「秩序」「均整」「対話」 ── 古典派音楽を一言で語るとすれば、この3つの言葉がふさわしいだろう。バロック時代の激しく装飾的な音楽を経て、18世紀後半に登場したのは、理性と美意識に裏打ちされた音楽の世界である。
この時代は、音楽が“自然と調和する芸術”として捉えられ、形式の美しさや論理的構造が重視された。まるで建築のように組み上げられた音楽。だがそこには、決して冷たくはない、人間らしい感情の揺らぎが秘められていた。
今回は、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンという“古典派三巨頭”の音楽をたどりながら、18世紀末に花開いた音楽の黄金時代を探る。
「古典派」とは何か ── 理想と現実の均衡点
「古典派」という言葉は、ラテン語の“classicus(模範的な、第一等の)”に由来する。芸術においては“永続的な価値を持つ様式”を意味し、音楽においては約1750年から1820年ごろを指す。バロックの最後を飾ったバッハが亡くなったのが1750年。それを区切りに、音楽はより簡潔で論理的なスタイルへと移行していった。
当時のヨーロッパ社会では、啓蒙思想が広がり、市民階級が台頭し始めていた。音楽は王侯貴族のためのものから、一般市民の“教養”や“娯楽”へと変化していく。その変化のなかで生まれたのが、ソナタ、交響曲、弦楽四重奏といった“古典派形式”である。
ソナタ形式とは?音楽に「起承転結」が生まれる
この時代の楽曲構造を支えたのが、いわゆるソナタ形式である。
ソナタ形式はざっくり言えば「テーマAとBを提示し、対話させて、最後にまとめる」というスタイルである。まるでストーリーのように音楽が進行することで、聴く側は理論的な満足と感情の共鳴の両方を得ることができる。
この構造によって、音楽は“背景のある響き”となり、単なる美しい音の連なりから、“語りかける芸術”へと進化した。
父ハイドン、形式の発明者
フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732–1809)は、ソナタ形式、交響曲、弦楽四重奏といった古典派の様式を確立した“音楽の父”である。ウィーン郊外の宮廷に仕えた彼は、孤立した環境の中で自由に、そして実験的に音楽を育てていった。
ハイドンの音楽は、明快で親しみやすく、時にユーモラスでさえある。形式美と人間味の絶妙なバランスが、今も多くの演奏家たちを魅了している。
ハイドン《交響曲第94番「驚愕」第2楽章》静かな冒頭に突如フォルテの「びっくり音」。ウィットと構成美の見事な融合。
モーツァルト、神の子と称された人間
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756–1791)は、天才として語られることの多い存在である。確かに、幼少期から天才ぶりを発揮し、膨大な作品を残した彼は“神の祝福”のような存在だった。
しかし同時に、彼の音楽には驚くほど人間的な苦悩、孤独、諦め、そして希望が織り込まれている。軽やかに聞こえる旋律の奥にある、深い情緒。その“両義性”こそが、モーツァルトの真骨頂である。
モーツァルト《ピアノ協奏曲第21番第2楽章》夢のように美しい旋律。映画『愛と哀しみのボレロ』でも使われた名曲。
若きベートーヴェン、古典の枠を壊し始める
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770–1827)は、古典派最後の巨匠であり、ロマン派の扉を開いた革命家でもある。
彼の初期の作品は、ハイドンやモーツァルトの影響を受けつつも、すでに内面からの激しい表現欲求が感じられる。特に《交響曲第3番「英雄」》以降、形式を拡張し、感情のダイナミズムを前面に押し出すスタイルへと進んでいった。
だが本稿ではあえて、“古典派の枠の中”にあるベートーヴェンを紹介したい。厳格な枠組みの中に宿る、爆発寸前の情熱こそが彼の初期作品の魅力である。
ベートーヴェン《ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」第2楽章》静かで慈しみに満ちた旋律。内に秘めた感情の強さを感じる珠玉の楽章。
音楽の聴き方が変わった時代
古典派の時代、音楽は“聴くもの”として確立された。それまでの音楽は、宗教や儀式の一部、あるいは王侯貴族の娯楽として機能していた。だが18世紀後半から、市民がホールで音楽を聴くという習慣が芽生えた。出版された楽譜を買い、自宅で演奏する。評論やレビューが生まれ、演奏家が「解釈」を持つようになった。
つまり、音楽が“社会的な言語”として独立したのがこの時代である。
まとめ:形式と感情の“黄金比”
古典派音楽は、形式美と感情の均衡がもたらす「理想のバランス」を体現している。それはまるで、よく設計された建築のように、細部まで構築された美しさを持ちながら、訪れる人にとっては心地よく、親しみやすい空間でもある。
ハイドンの実験精神、モーツァルトの人間性、ベートーヴェンの情熱 ── そのすべてが、音楽という普遍的な言語を「世界共通の芸術」へと押し上げたのである。

Sera H.:時代を越える音楽案内人/都市と田舎、過去と未来、東洋と西洋。そのあわいにいることを好む音楽ライター。クラシック音楽を軸にしながら、フィールド録音やアーカイブ、ZINE制作など多様な文脈で活動を展開。書くときは、なるべく誰でもない存在になるよう心がけている。名義の“H”が何の頭文字かは、誰も知らない。